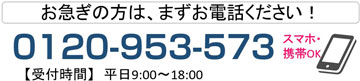オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り
- 2021年5月5日公開

経営者の皆さんは、節税商品として「オペレーティングリース」の紹介を受けたことはありますか。
オペレーティングリースのよくあるスキーム図では、登場人物が込み入っており、結局何をしているか、初見ではなかなか分からないと思います。
この記事では、オペレーティングリースは結局何をしているのか、噛み砕いて説明します。
また、実際にオペレーティングリースを使ってみたいとお考えの経営者の方に向けて、以下の順で解説します。
- どのような会社がオペレーティングリースを活用すべきか?
- オペレーティングリースにはリスクはないのか?
- オペレーティングリースを活用するにはどうしたらよいか?
桐敷匠
最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)
- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日
- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日
- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日
目次
1. オペレーティングリースとは?
節税商品としてのオペレーティングリースは、ざっくり言うと以下の一連の取引を指します。なお、実際にはもっと詳細で複雑なしくみなのですが、イメージしやすくするため、理論的な正確性は多少犠牲にしています。ご了承ください。
- 節税したい中小企業が資金を出し合い、航空機等のリース用資産を共同で購入する
- 購入したリース用資産を航空会社等に数年間貸し出し、毎年リース料収入を得る
- リース期間終了後、リース用資産を売却する
会計用語でもオペレーティングリースという用語があるものの、節税商品としてのオペレーティングリースと会計用語とでは、別物と考えた方がよいです。
2. オペレーティングリースはなぜ節税になるのか?
オペレーティングリースが節税商品と呼ばれるのは、航空機等の購入代金が減価償却費として費用計上できるからです。
特に購入初年度は、定率法という計算方法により、多くの減価償却費を計上できます。
本業で突発的に大きな利益が出そうな年に、航空機等の減価償却費を計上する事により、利益や利益に伴って発生する法人税を打ち消すことができます。
一方、リース期間終了後に航空機等を売却する際は大きな利益が発生します。
利益が発生するのは、航空機等のリース用資産は社用車等と比較すると市場価格が下がりづらく、リース後も高値で売却できるためです。
このため、オペレーティングリースは節税商品と言われますが、実際には課税の繰り延べに過ぎません。リース期間終了後に利益を相殺するだけの損金を発生させる何らかの予定が無ければ、最終的には税金を納める事になります。
2.1. 社用車等を購入する場合との違い
実は、オペレーティングリースは社用車等の事業用資産を購入するのと、途中までは似ています。
社用車が経費になる事は直感的に分かる経営者の方も多いと思いますので、ここでは社用車とオペレーティングリースを比較しながら説明します。
| 社用車 | オペレーティングリース | |
| ① 資産取得 | 社用車を購入する。 購入した社用車は減価償却費として経費になる。 |
航空機等のリース用資産を購入する。 購入したリース用資産は減価償却費として経費になる。 |
| ② 資産利用 | 購入した社用車を自社の営業活動等に使用する。 | 購入したリース用資産を航空会社等に数年間貸し出し、毎年リース料収入を得る。 |
| ③ 資産売却 | 老朽化した社用車を廃車、又は下取りに出す。 | リース期間終了後、リース用資産を売却する。 |
上記のうち、①は全く同じです。また、②は資産を利用して何らかの価値を得ているという点でよく似ています。
両者が大きく違うのは③です。
老朽化した社用車は廃車するか、二束三文で下取りに出すことになります。
一方、リース用資産は前述の通り市場価格が下がりづらいので、高値での売却が見込めます。
従って、利益が出たからと言って無目的に社用車等を購入するくらいなら、オペレーティングリースを検討してもよいかもしれません。
3. どんな会社がオペレーティングリースを活用すべきか?
冒頭でお伝えした通り、オペレーティングリースは課税の繰り延べに過ぎません。
オペレーティングリースにより、一次的に目先の税金を減らしても、数年後に大きな税額が発生することになります。
従って、オペレーティングリースを活用する意味がある会社は、「目先で大きな利益が出ている」かつ「数年後に大きな支出の予定がある」の両方を満たす会社です。
大きな支出予定としては、例えば社長の退職金を出す、新事業を始める、等です。
他にも、事業承継・相続税対策として、自社株式の評価額を一時的に引き下げるために活用する方法があります。
ただし、オペレーティングリースには様々なリスクがあります。
これらのリスクもよく検討の上、それでもメリットが大きいと判断した時だけオペレーティングリースを検討しましょう。
具体的なリスクの内容は次節で説明します。
4. オペレーティングリースにリスクはないのか?
オペレーティングリースにはリスクがあります。
ここでは、必ず検討すべき主要なリスクと対処法を説明します。
4.1. 資金繰りリスクと対処法
リース用資産の購入のために支出した資金はリース期間終了後、リース用資産の売却代金という形で最終的には戻ってきます。
ただし、リース期間中は途中売却できない契約になっている事が通常ですので、その間は資金が拘束されます。
オペレーティングリースは余裕資金の範囲で行うようにしましょう。
4.2. 元本割れリスクと対処法
オペレーティングリースには元本保証がありません。
つまり、リース用資産が高値で売却できると言っても、当初の支出額が戻ってくる保証はありません。
この理由は大きく分けて2つあります。
1つ目の理由は、円高です。
リース用資産の多くは海外で売買する事になります。
これは、オペレーティングリースでよく使われる航空機、船舶、輸送コンテナが世界中を駆け巡っており、取引相手も基本的には海外の航空会社等になるためです。
従って、リース用資産の購入時点よりも売却時点の方が円高に振れている場合は為替差損を受ける事になります。
為替リスクを嫌うのであれば、為替ヘッジを行う事も一案です。(為替ヘッジもコストがかかります。)
2つ目の理由は、リース先企業の経営破綻です。
実は、リース期間終了後の資産の売却先はリース先企業であるケースが多いです。
リース先企業が破綻した場合は当然リース先企業に購入してもらえないので、中古市場で買い手を探すことになるものの、想定していた価格で買い手が見つからない事もあります。
このようなことの無いように、リース先を国営航空会社等の安定企業にする等の対策を取るのが通常ですが、それでも経営破綻するケースはあります。
最近では、コロナ禍によりモーリシャス航空等が破綻しています。
5. オペレーティングリースを活用するには?
出資者である中小企業はオペレーティングリースに必要なノウハウを持っていませんので、普通は仲介業者に頼むことになります。
仲介業者側で資金の出し手の募集、リース用資産の購入、借り手の募集、売却等の一切を対応してもらえるので、出資者側はお金を出すだけで大丈夫です。
仲介業者は大手リース会社のほか、オペレーティングリース専業の会社(株式会社FPG、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー、etc)も存在します。
これらの企業は税理士と繋がりを持っている事が多いので、顧問税理士に紹介を頼むのも良いでしょう。
まとめ
オペレーティングリースは多額の減価償却費を計上できるため、課税の繰延の手段としては優秀です。
ただし、オペレーティングリース固有のリスクもありますので、しっかりリスクを検討の上、活用するようにしましょう。
関連記事
-

定番として取り上げられる節税策の中に、倒産防止共済が挙げられます。 (経営セーフティ共済とも呼ばれます) 倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産防止を趣旨とする共済ですが、実務においては節税策として使われることもよくあります。 しかし実は、倒産防止
-

税金対策として、中古自動車を購入すると良い、という話を聞いたことがあると思います。 しかし、そのしくみを分かっていないと、税金対策したつもりが、まったく効果がないどころか、むしろ損をしてしまうリスクがあります。 そこで今回は、中古自動車を購入することが
-

個人事業主の方は、原則として確定申告をする必要があります。 所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告の方が有利だということは、多くの方がご存知だと思います。 ただし、どのくらい青色申告の方がお得なのか、どういう方に青色申告が認められ
-

経営者の皆さんは、節税商品として「オペレーティングリース」の紹介を受けたことはありますか。 オペレーティングリースのよくあるスキーム図では、登場人物が込み入っており、結局何をしているか、初見ではなかなか分からないと思います。 この記事では、オペレー
-

貸倒損失とは、売掛金が回収できなかった時に、費用として処理する方法です。 得意先から売掛金が入金されない事態となった時、まずは回収する努力が必要です。 それでもどうしても売掛金の回収ができない場合、売掛金の貸倒損失を損金算入できないかを検討しましょう。
-

会社から役員に対する報酬は、毎月の定額報酬ではなく役員賞与として受け取った方がお得という話を聞いたことは無いでしょうか。 この話は、場合によっては事実と言えます。 支給額の水準によっては、社会保険料が抑えられ、その分だけお得になるケースがあるからで
-

貸倒引当金とは、売掛金の回収できない金額を事前に見込んでおいて、費用処理することです。 売掛金の回収が既にできなくなっている場合は貸倒損失を計上することにより、税金を減らすことができます(詳しくは「貸倒損失とは?回収できない債権を費用化できる条件」を
-

小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点
小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主の方で、所得税・住民税を節税したい、老後の資金の効率的な準備をしたい、と悩んでいる方におすすめしたい制度です。 手元に残るお金は、年収が800万円の場合、例えば毎月7万円の掛金を20年かけると、共済をやった
-

持ち家を買うと「住宅ローン控除」により所得税が下がるという事は皆さんもよくご存知と思います。 住宅ローン控除は、数ある所得税の控除制度の中でも節税効果の非常に大きな制度です。 しかし、住宅ローン控除の具体的な内容までは不動産会社等から説明されないこ
-

大きな利益が出ており、多額の法人税が発生する見込みの会社では、期末に駆け込みで経費を立てて、法人税額を減らそうとする事がよくあります。 典型的には、家賃等をまとめて前払いする(前払費用といいます)ケースです。 しかし、実際には、前払費用を支払ったタ