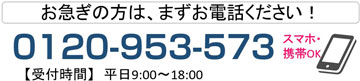小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点
- 2020年8月11日公開
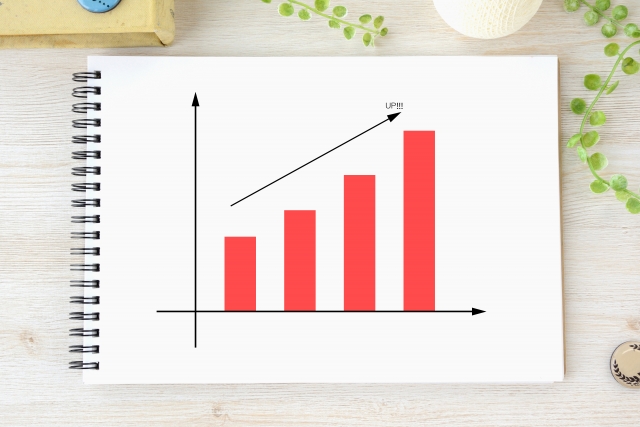
小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主の方で、所得税・住民税を節税したい、老後の資金の効率的な準備をしたい、と悩んでいる方におすすめしたい制度です。
手元に残るお金は、年収が800万円の場合、例えば毎月7万円の掛金を20年かけると、共済をやった場合とやらない場合では、返ってくる掛金と節税効果を併せて1.4倍になる事があります。
ただし、メリットばかりではなく、損をするリスクもありますので、メリットと注意点をお伝え致します。
相馬雅巨
最新記事 by 相馬雅巨 (全て見る)
- 小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点 - 2020年8月11日
- 交際費とは!?経費にするためのポイントまとめ - 2020年7月10日
- 銀行融資とは?審査に通るために知っておきたいポイント - 2020年6月1日
目次
1.小規模企業共済とは
この制度は、中小企業の役員・個人事業主ならその多くが対象となります。
掛金がひと月1,000円から7万円 まで選択でき、無理なく自分の収入に応じた積立が可能です。
また、掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税の節税となります。
積立したお金を受け取る際には、税金が安い方法で受け取る事が可能で、税金が0円となる事もあります。
困ったときは低い利率で借入を行う事もできますし、節税効果プラス退職時などの積立としてお得です。
それから、経済産業省の所管する独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下中小機構)が実施機関となっており、国が行っておりますので、一定の信用もあります。
これから詳しく見ていこうと思います。
2.小規模企業共済のメリット
小規模企業共済の主なメリットは以下の通りです。
- 掛金が全額所得税及び住民税の所得控除となり、節税になる
- 退職時に受け取る共済金の所得税が安く、節税になる
- 掛金が増額された金額で返ってくる
その他として、
- 掛金の範囲内で借入れができる
- 掛金月額を1,000円から7万円までの範囲内で自由に選択できるため、無理のない金額から始められ(増額減額可)
- 支払方法の変更可(月払い・半年払い・年払い)、掛金の払込が困難になったとき、払込の一時中止ができる
- などのメリットがあります。
メリット1|払込金額が全額(最大84万円)所得税及び住民税の所得控除となり、節税になる
これが一番のメリットです。
小規模企業共済は、月の掛金を最大7万円まで1,000円刻みで設定できます。
この掛金の全額を、所得税及び住民税の計算上、所得控除といって、経費のように、収入金額から控除する事ができます。
つまり、毎年、最大で、
- 7万円×12ヶ月=840,000円
を所得控除できるのです。
これは、年収の高い人程、節税効果が高くなります。
なぜなら、所得税は、所得が高くなるほど、段階的に税率が高くなっていくしくみになっているからです(超過累進税率)
例えば、所得税率が20%の方で、年収800万円、家族は専業主婦の配偶者と高校1年の子の2人、各種所得控除(生命保険料控除や地震保険料など)17万円の方の場合、所得税は約521,200円、住民税は約495,100円です。
この方が、小規模企業共済を毎月7万円12ヶ月掛けた場合、所得税と住民税がどの程度軽減されるか、計算してみると、以下のようになります。
●所得税の軽減額
所得税については、
- 84万円×20%=168,000円
が軽減されます。
●住民税の軽減額
住民税については、一律10%のため
- 84万円×10%=84,000円
が軽減されます。
以上、所得税と住民税で1年あたり総額約255,600円、20年ならば総額約5,112,000円の節税になります。
メリット2|掛金が増額された金額で受け取れる
小規模企業共済は、長期間加入していると、掛金が増えて返ってきます。
例えば、2020年7月から加入し、2040年6月に退職して共済金を受け取った場合のケースだと、
- 毎月掛金3万円、加入期間20年
- 掛金合計額 7,200,000円
- 共済金A(事業廃止等) 8,359,200円(掛金より16.1%増額)
- 共済金B(退職等) 7,976,400円(掛金より10.7%増額)
となっており、10%以上増えて返ってきます。
なお、共済金の種類と、請求事由は、法人の役員の場合は以下の通りです。
| 種類 | 請求事由 |
| 共済金A | ・法人が解散した場合 |
| 共済金B | ・病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合(※) ・共済契約者の方が亡くなられた場合 ・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) |
| 準共済金 | ・法人の解散、病気、怪我以外の理由により、 または65歳未満で役員を退任した場合 |
| 任意解約 | ・任意解約 ・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) |
(※)平成28年3月以前に、病気または怪我以外の理由による退任をしたときは、「準共済金」となります。
- 共済金A:会社を解散して役員の地位を失った場合
- 共済金B:病気やケガで役員をやめた場合、65歳以上で役員をやめた場合
- 準共済金:65歳未満で役員をやめた場合、病気、ケガ、会社の解散以外の理由で役員をやめた場合
- 解約手当金:役員をやめずに共済だけをやめた場合、掛金を12ヶ月以上滞納した場合
となっています。
このうち、特に、解約手当金については、元本割れのリスクが大きくなっています。
したがって、途中で解約せずに済むよう、無理なく払い続けられる額から始めることが大切です。
詳しくは「3.小規模企業共済の注意点」にて後ほど説明します。
メリット3|共済金を受け取る際の税金が安い
一括で受け取る際の税金が安い事も大きなメリットです。
一括で共済金を受け取る際に退職所得として扱われ、税金が抑えられます。
また、場合によってはゼロになることもあります。
なぜなら、退職所得は積立期間が20年なら800万円まで税金がかからないからです。
つまり、退職所得の計算は、
(収入-退職所得控除額)×1/2
となっています。
したがって、掛金が20年以下なら退職所得控除の額は「40万円×掛金年数」となります。
収入がこの退職所得控除額以下なら、税金がかかりません。
ただし、退職所得控除80万円に満たない場合は80万円となります。
例えば3万円を46歳から66歳まで20年間振り込んだ後、役員を退任したケースを考えてみましょう。
- 掛金合計:30,000円×(20年×12ヶ月)=7,200,000円
- 受け取れるお金(共済金B):7,976,400円
退職所得控除の計算例(収入金額から控除する金額)
40万円×20年=8,000,000円
退職所得の計算
(7,976,400円-8,000,000円)×1/2=0円
上記の計算の通り0円になります。
控除額にまだ余裕があるのがわかるように、とても税金が安くなる制度となっています。
なお、共済金の受け取り方は、以下のうちから選ぶことができます。
- 一括で受け取る
- 分割で受け取る
- 一括受け取りと分割受け取りの併用
この中で最も有利なのは、一般的には、一括で受け取る方法です。
なぜなら、上述のように退職所得控除を受けられるからです。
ただし、ケースバイケースなので、受け取ることになった時に、計算してみることをおすすめします。
なお、分割受け取りや、一括受け取りと分割受け取りの併用で受け取る場合には、受け取る金額が300万円以上から選択可、などの条件がありますのでご注意下さい。
その他のメリット
契約者貸付
災害や資金繰りの悪化、事業承継、廃業準備などの、もしものときに、掛金の範囲内(掛金の払込みの月数により掛金の7~9割)で借入をすることができます。
借入利率はかなり低くなっています。詳しくは契約書貸付けの最新の利率についてをご覧下さい。
掛金設定の自由度
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で変更する事ができます。
ご自身の手元資金に合わせて払込金額を設定して頂くと良いと思います。
なお、資金に余裕のある方は、前納して頂くと、一定割合の前納減額金を受け取る事も可能です。
また、月払い、半年払い、年払いと選択する事ができます。
一般的には月払いだと思いますが、売上等の入金が半年単位や季節単位の方などは、入金のタイミングに合わせて掛金を払込みする事もできます。
それから、掛金の払込みを止めることが出来ます。
以下のいずれかの状況で、掛金の払込みが困難な場合には、半年または1年の間、掛金の払込みを止めることができます。
- 所得(収入)がない場合
- 災害に遭遇した場合
- 入院中の場合
これまでは小規模企業共済のメリットをお伝えして来ましたが、これからは小規模企業共済の注意点をお伝え致します。
3.小規模企業共済の注意点
メリットだけではなく、注意点もあります。
この注意点に留意して頂くと、より小規模企業共済のメリットを享受、あるいは、加入検討に役立つと思います。
3.1元本割れのリスク
掛金の払込み期間が20年(240ヶ月)未満の任意解約した場合は、掛金合計額を下回ります。
なお、任意解約とは、役員は続けるが共済自体を解約することや、掛金を12ヶ月以上滞納した場合が当てはまります。
また、20年(240ヶ月)以上でも、払込みを一時中止していた場合、掛金の払込み金額を変更した場合があって、任意解約した場合には、受け取れる解約手当金(任意解約時の共済金の名称)が掛金合計額を下回る事がありますのでご注意下さい。
詳しくは「中小機構HPの共済金(解約手当金)について」をご覧下さい。
そこで、元本割れのリスクへの対処法としては、
- 何事もなければ65歳まで役員を続ける前提で共済を続ける
- 掛金は無理なく払い続けられそうな額に設定する
以上のことを守ると、元本割れをせずに共済金を受け取れます。
3.2掛金払込み期間が短いと共済金が受け取れない場合がある
受け取れる共済金の種類が状況に応じて変わります。
「メリット2|掛金が増額された金額で受け取れる」にある表及び受け取れる事由を参考にご覧ください。
共済金Aと共済金B
共済金A及び共済金Bは、掛金払込み月数が6ヶ月未満の場合は、受け取る事ができません。
準共済金
準共済金は掛金払込み月数が12ヶ月未満の場合は、受け取る事ができません。
解約手当金
もっとも注意が必要なのが、解約手当金です。
以下の3つのデメリットがあります。
- 解約手当金は、掛金払込月数が12ヶ月未満の場合、受け取れない(掛け捨て)
- 20年未満で解約すると、掛金総額よりも低い額しか返ってこない
- 共済金の受け取りに比べて税金が高くなる
なぜなら、退職所得という制度ではなく、一時所得という制度が対象となるためです。
つまり、一時所得の計算方法は、
「収入金額」-「収入を得るために支出した金額」-50万円
となります。そして、その1/2が、課税対象となります。
「収入金額」は解約手当金となります。
「収入を得るために支出した金額」は0円となりますので、「解約手当金-50万円」が一時所得の所得金額となり、ここに課税されます。
例えば、2020年7月から加入し、2030年6月に任意解約をして解約手当金を受け取った場合のケースだと、
- 毎月掛金3万円、加入期間10年
- 掛金合計額 3,600,000円
- 解約手当金(任意解約) 3,060,000円(掛金より15%減額)
一時所得の計算
3,060,000円-0円-50万円=2,560,000円
2,560,000円×1/2=1,280,000円
上記が一時所得の所得金額となります。
なお、今までの掛金が「収入を得るために支出した金額」となると思うかもしれませんが、毎年度、掛金は所得控除されてきていますので、0円となります。
以上、任意解約は、返ってくるお金が少ない上、税金も高くなります。
なので、確実に支払い続けられる額から始めることをおすすめします。
3.3加入できない場合がある
ほとんどの中小企業の役員や個人事業主が加入できますが、従業員数が多い場合には加入できない場合があります。
業種によっても違いますので、詳しくは「中小機構HPの加入資格」をご覧下さい。
まとめ
小規模企業共済は、掛金が全額、所得税及び住民税の所得控除になる上、共済金受取時の税金が安くなるため、節税効果がとても高い制度となっています。
国が運営している制度であるため、一定の信用がおけます。
ただし、途中でやめると(任意解約)共済掛金の元金が目減りするリスクが大きいので、無理なく支払い続ける額から始めることをおすすめします。
小規模企業共済を使って、高い節税効果を享受しながら、老後の資金等の効率的な準備をしていきましょう。
関連記事
-

個人事業主の方は、原則として確定申告をする必要があります。 所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告の方が有利だということは、多くの方がご存知だと思います。 ただし、どのくらい青色申告の方がお得なのか、どういう方に青色申告が認められ
-

経営者の皆さんは、節税商品として「オペレーティングリース」の紹介を受けたことはありますか。 オペレーティングリースのよくあるスキーム図では、登場人物が込み入っており、結局何をしているか、初見ではなかなか分からないと思います。 この記事では、オペレー
-

税金対策として、中古自動車を購入すると良い、という話を聞いたことがあると思います。 しかし、そのしくみを分かっていないと、税金対策したつもりが、まったく効果がないどころか、むしろ損をしてしまうリスクがあります。 そこで今回は、中古自動車を購入することが
-

貸倒損失とは、売掛金が回収できなかった時に、費用として処理する方法です。 得意先から売掛金が入金されない事態となった時、まずは回収する努力が必要です。 それでもどうしても売掛金の回収ができない場合、売掛金の貸倒損失を損金算入できないかを検討しましょう。
-

定番として取り上げられる節税策の中に、倒産防止共済が挙げられます。 (経営セーフティ共済とも呼ばれます) 倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産防止を趣旨とする共済ですが、実務においては節税策として使われることもよくあります。 しかし実は、倒産防止
-

持ち家を買うと「住宅ローン控除」により所得税が下がるという事は皆さんもよくご存知と思います。 住宅ローン控除は、数ある所得税の控除制度の中でも節税効果の非常に大きな制度です。 しかし、住宅ローン控除の具体的な内容までは不動産会社等から説明されないこ
-

小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点
小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主の方で、所得税・住民税を節税したい、老後の資金の効率的な準備をしたい、と悩んでいる方におすすめしたい制度です。 手元に残るお金は、年収が800万円の場合、例えば毎月7万円の掛金を20年かけると、共済をやった
-

大きな利益が出ており、多額の法人税が発生する見込みの会社では、期末に駆け込みで経費を立てて、法人税額を減らそうとする事がよくあります。 典型的には、家賃等をまとめて前払いする(前払費用といいます)ケースです。 しかし、実際には、前払費用を支払ったタ
-

貸倒引当金とは、売掛金の回収できない金額を事前に見込んでおいて、費用処理することです。 売掛金の回収が既にできなくなっている場合は貸倒損失を計上することにより、税金を減らすことができます(詳しくは「貸倒損失とは?回収できない債権を費用化できる条件」を
-

会社から役員に対する報酬は、毎月の定額報酬ではなく役員賞与として受け取った方がお得という話を聞いたことは無いでしょうか。 この話は、場合によっては事実と言えます。 支給額の水準によっては、社会保険料が抑えられ、その分だけお得になるケースがあるからで