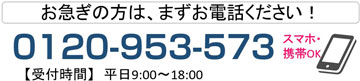倒産防止共済とは?節税ではなく課税の繰延です
- 2020年9月9日公開

定番として取り上げられる節税策の中に、倒産防止共済が挙げられます。
(経営セーフティ共済とも呼ばれます)
倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産防止を趣旨とする共済ですが、実務においては節税策として使われることもよくあります。
しかし実は、倒産防止共済は課税の繰延に過ぎず、厳密には節税策とは言えません。
(繰延も、目先の税額を抑えられるというメリットはあります。)
それにも関わらず節税策の定番となっているのは、顧問税理士等から説明を受けた上で、メリットが非常に大きいと感じるからだと思います。
そこで、この記事では、倒産防止共済の税務上の大まかな取扱いをご説明します。
また、倒産防止共済には、「取引先の倒産への備えができる」「課税の繰延ができる」というメリットがあるものの、加入する場合には幾つか注意点もあるため、それら注意点についても合わせてご説明します。
桐敷匠
最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)
- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日
- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日
- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日
目次
1. 倒産防止共済とは|本来の目的は連鎖倒産防止
経営セーフティ共済を活用した節税方法を税理士が解説!連鎖倒産を防いで総額800万円まで全額損金算入
倒産防止共済とは、加入者が取引先倒産防止という事態に直面した際に、緊急融資を受けることができる制度です。
1年以上営業している中小企業であれば、基本的に加入することができます。(※)
※資本金額や従業員数による制限があります。詳細は中小機構ウェブサイトをご確認下さい。
加入者は取引先の倒産に備えて毎月掛け金を納めていき、いざ実際に取引先が倒産してしまった場合には、無担保・無保証人の条件で、それまでの掛け金総額の10倍(最高8,000万円)まで融資を受けることができます。
月々の掛け金は5,000円から20万円まで選択可能であり、後から月単位で変更もできるため、少額から気軽に始められることも特徴です。
また、掛け金は掛け捨てではなく、共済解約時には掛け金が全額返金(※)されます。
※早期解約した場合や途中で融資を受けた場合は全額返金されません。後述します。
1.1. 倒産防止共済の税務上の取り扱い
上記でも説明した通り、倒産防止共済は先に掛け金を納めていき、解約時には掛け金が全額返ってくる仕組みになっています。つまり、実質的には何か費用を支払ったというよりは、社外に掛け金を預けているに過ぎません。
ところが、この共済には税務上の優遇措置が設けられており、掛け金を納めたタイミングで全額損金にすることができます。
倒産防止共済に節税効果があるとされているのは、この「掛け金が損金になる」という事実を指しています。
ただし、ここまでで話が終わっていれば確かに節税効果があると言えるのですが、実際には続きがあります。
実は、共済解約時に受け取る解約手当金は課税対象であり、益金算入されることとなるのです。
このため、掛け金納付時に損金算入されるものの、解約時に同額が益金に算入されるため、トータルの損益ではプラスマイナスゼロとなり、法人税額ないし所得税額は変わらない、つまり節税効果はないことになります。
一方で、掛け金納付による損金算入が先に来る仕組みのため、当初の税額は減る、つまり課税の繰延効果はあります。
また、保険とは異なり、解約の時期は会社側が自由に選べますので、資金繰りに問題が無ければ、解約しないことで課税をずっと繰り延べる事も可能です。
1.2. 決算対策には最適
将来はともかくとして、決算日ぎりぎりで決算対策したいという場合には倒産防止共済は最適です。
これは、掛け金最大額の20万円の12ヶ月分を前払いすると、最大で240万円まで一気に損金にできるからです。
このような時に、ひとまず倒産防止共済に加入するのは有りです。
2. 倒産防止共済加入時の注意点
倒産防止共済には加入時に検討すべき注意点が3つあります。
・資金繰りに影響がある
・すぐに解約した場合、掛け金の全額又は一部が戻らない
・解約後、再加入はできるが、再加入直後6か月は借り入れができない
それぞれ順を追って説明します。
2.1. 資金繰りに影響がある
掛け金が損金にできると言っても、掛け金納付によって現実にキャッシュアウトが発生します。このため、手元資金がそれほど潤沢でない場合は掛け金納付が資金管理上の負担になる可能性があります。
冒頭でも記載した通り、月々の掛け金は5,000円から20万円まで選択可能であり、後から月単位で変更もできますので、将来の資金繰りが不透明な場合は少額から始めると良いでしょう。
2.2. 一定の場合、掛け金の全額または一部が戻らない
記事冒頭で、掛け金は解約時に全額戻るとご説明しましたが、これは「掛け金の納付を40か月以上続けていること」及び「倒産防止共済から融資を受けていない事」が条件になります。
逆に言えば40か月未満で解約した場合は掛け金が一部戻って来ない事となります。
特に、12か月未満で解約した場合には全額が返ってきません。
従って、最低でも12か月、できれば40か月以上続けるつもりで加入するようにしましょう。
さらに、融資を受けた場合には融資額の1/10が掛け金から取り崩されるルールになっていますので、この場合もやはり全額は返ってこない事となります。
もちろん、資金繰りに詰まってしまっては元も子もないため、必要になれば躊躇なく融資を受けるべきですが、他に何か手段が無いか確認はすべきです。
2.3. 解約後、再加入はできるが、その後6か月は借り入れができない
倒産防止共済は、解約後の再加入は自由です。(加入条件を充たす必要はあります)
ただし、再加入後6ヶ月間は共済金の借り入れができません。
取引先倒産時に借り入れができない、となっては加入の意味がありませんので、解約時は慎重に判断をしましょう。
3. (参考)倒産防止共済はこんな特典も|運転資金借入
実は、倒産防止共済には、一時貸付金制度と言って、取引先が倒産しなくても臨時的に運転資金の借入ができる制度があります。
借入限度額は最大でも760万円と、取引先倒産時と比べると少額ですが、無担保・低金利(2020年現在0.9%)という好条件ですので、急に資金が必要になった時は借入を検討してもよいでしょう。
まとめ
倒産防止共済は取引先の倒産への備えができる、課税の繰延ができるというメリットがあるため、特に貸倒れリスクの高い業種では加入を前向きに検討してもよいでしょう。
一方、資金が一定期間拘束されることになりますので、あまり貸倒れのない場合には慎重に検討した方がよいかもしれません。
連鎖倒産防止という本来の活用法からすると、貸し倒れの心配がない業種にとっては必須ではないかも
しかし、
・利益の繰り延べの効果は高く、リスクも低い
・全額損金になる
・40ヶ月以上加入すれば全額戻ってくる
・解約のタイミングを自由に選べる
などのメリットが大きいことを考えると、資金繰りに支障をきたさない額で加入することをおすすめします。
関連記事
-

大きな利益が出ており、多額の法人税が発生する見込みの会社では、期末に駆け込みで経費を立てて、法人税額を減らそうとする事がよくあります。 典型的には、家賃等をまとめて前払いする(前払費用といいます)ケースです。 しかし、実際には、前払費用を支払ったタ
-

個人事業主の方は、原則として確定申告をする必要があります。 所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告の方が有利だということは、多くの方がご存知だと思います。 ただし、どのくらい青色申告の方がお得なのか、どういう方に青色申告が認められ
-

小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点
小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主の方で、所得税・住民税を節税したい、老後の資金の効率的な準備をしたい、と悩んでいる方におすすめしたい制度です。 手元に残るお金は、年収が800万円の場合、例えば毎月7万円の掛金を20年かけると、共済をやった
-

経営者の皆さんは、節税商品として「オペレーティングリース」の紹介を受けたことはありますか。 オペレーティングリースのよくあるスキーム図では、登場人物が込み入っており、結局何をしているか、初見ではなかなか分からないと思います。 この記事では、オペレー
-

貸倒損失とは、売掛金が回収できなかった時に、費用として処理する方法です。 得意先から売掛金が入金されない事態となった時、まずは回収する努力が必要です。 それでもどうしても売掛金の回収ができない場合、売掛金の貸倒損失を損金算入できないかを検討しましょう。
-

貸倒引当金とは、売掛金の回収できない金額を事前に見込んでおいて、費用処理することです。 売掛金の回収が既にできなくなっている場合は貸倒損失を計上することにより、税金を減らすことができます(詳しくは「貸倒損失とは?回収できない債権を費用化できる条件」を
-

定番として取り上げられる節税策の中に、倒産防止共済が挙げられます。 (経営セーフティ共済とも呼ばれます) 倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産防止を趣旨とする共済ですが、実務においては節税策として使われることもよくあります。 しかし実は、倒産防止
-

会社から役員に対する報酬は、毎月の定額報酬ではなく役員賞与として受け取った方がお得という話を聞いたことは無いでしょうか。 この話は、場合によっては事実と言えます。 支給額の水準によっては、社会保険料が抑えられ、その分だけお得になるケースがあるからで
-

税金対策として、中古自動車を購入すると良い、という話を聞いたことがあると思います。 しかし、そのしくみを分かっていないと、税金対策したつもりが、まったく効果がないどころか、むしろ損をしてしまうリスクがあります。 そこで今回は、中古自動車を購入することが
-

持ち家を買うと「住宅ローン控除」により所得税が下がるという事は皆さんもよくご存知と思います。 住宅ローン控除は、数ある所得税の控除制度の中でも節税効果の非常に大きな制度です。 しかし、住宅ローン控除の具体的な内容までは不動産会社等から説明されないこ