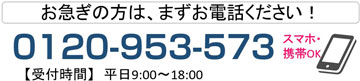事業承継税制とは?特例措置により税負担をゼロにできます
- 2020年6月28日公開
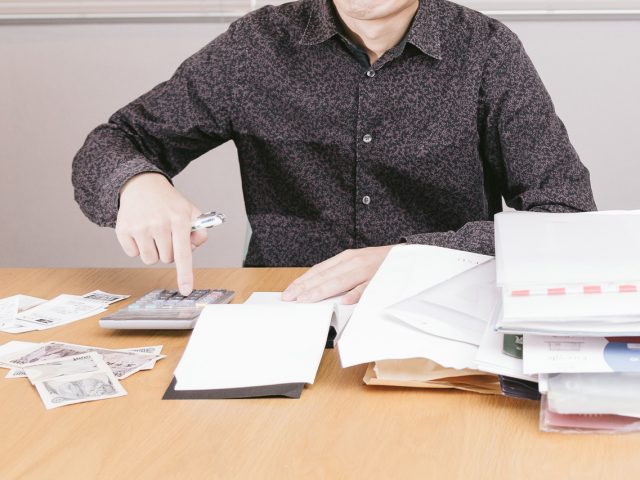
経営者にとって、次世代への事業承継は大きな悩みの一つです。
後継者の育成、相続税・贈与税の税金負担の問題、etc・・。
このうち、税金負担の問題は事業承継税制を利用することで解消できます。
従来、事業承継税制は使いにくい点が目立っていましたが、2027年までの期間限定で特例措置が設けられており、現時点では利用しやすいものとなっています。
この記事では事業承継税制のメリットをご紹介します。
また、実際に事業承継税制の利用を検討される方向けに、利用するための要件、必要手続き、注意点も併せてご紹介します。
桐敷匠
最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)
- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日
- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日
- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日
目次
1.事業承継税制のメリット
事業承継税制とは?特例措置により税負担をゼロにする方法
- 事業承継時の税負担がゼロになる
- 将来の課税リスクが軽減される
- 後継者が複数人でも利用できる
以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
1.1. 事業承継時の税負担がゼロになる
本来、自社株式を後継者に贈与した場合は贈与税、相続した場合には相続税が課税されるため、事業承継時には大きな税金負担が発生します。
しかし事業承継税制を利用した場合、事業承継時の税負担が大幅に軽減されます。
しかも、従来の制度では軽減額に一定の制限があり、最大でも5割程度までしか軽減されませんでしたが、現在施行されている特例措置では制限が撤廃され、事業承継時の税負担は完全にゼロになります。
1.2. 将来の課税リスクが軽減される
事業承継税制とは、実質的には税負担を免除するものですが、形式的には納税猶予(課税の繰延)の形をとっています。
これはどういうことかというと、事業承継時の税負担が軽減/免除される一方で、一定の要件を満たせなくなった場合には後継者側で納税の義務が生じます。
「一定の要件」の中で実務上よく問題になるのは「雇用要件」です。
雇用要件:事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持すること
雇用維持は経営者にとって大きな負担になりかねないため、事業承継税制の利用に二の足を踏むケースが続出していました。
これを踏まえて、特例措置では雇用要件が実質的に撤廃されるなど繰り延べ要件が緩和されており、要件を充たし続ける事も難しくないため、実質的には課税の繰り延べではなく、免税と言っても差し支えないものとなっています。
1.2.1. 要件を充たせなくなっても、かなりの確率で実質免除してもらえる!
さらに、仮に要件を満たせなくなったとしても、経営悪化による廃業等、一定の場合には税負担の減免/免除措置が用意されており、課税リスクが軽減されています。
より詳細な、減免/免除措置を受けるためのは中小企業庁HPをご確認下さい。
1.3. 後継者が複数人でも利用できる
従来の事業承継税制では先代経営者、後継者共に一人の場合しか利用することができませんでしたが、特例措置では複数の経営者から3人までの後継者への事業承継でも利用する事ができるように要件が緩和されています。
現実問題として後継者が複数人というケースは多いため、適用できるチャンスが広がったと言えます。
2. 事業承継税制を利用するための要件
特例措置を利用するための要件は全部で4つあります。
実務上特に問題になるのは「後継者の要件」と「先代経営者の要件」です。
制度を利用する場合はこれら要件を充たしているかよくご確認下さい。
2.1. 後継者の要件
後継者の要件としては、会社経営者の後継者としての実質を備えている事が要求されます。
これは、事業承継税制の趣旨が、円滑な事業承継をさせることによる、中小企業の存続にあるためです。
相続の場合、後継者が決まっていないうちに不慮の事態に至るケースがあるため、贈与の場合と比べると要件が少し緩和されています。
| 要件 | 贈与の場合 | 相続の場合 |
| 会社代表権 | 贈与時点で会社の代表権を持っている。 | 相続後5か月後の時点で会社の代表権を持っている。 |
| 年齢 | 20歳以上 | 20歳以上 |
| 役員在任 年数 |
3年以上 | 相続直前時点で役員であった事 ※先代経営者が60歳未満で死亡した場合は不問 |
| 議決権 | ■後継者が一人の時 筆頭株主である事■後継者が2~3人の時 以下を両方充たす。 ・各後継者が議決権10%以上を保持している ・各後継者が親族等の中で議決権を一番多く保持している |
■後継者が一人の時 筆頭株主である事■後継者が2~3人の時 以下を両方充たす。 ・各後継者が議決権10%以上を保持している ・各後継者が親族等の中で議決権を一番多く保持している |
2.2. 先代経営者の要件
先代経営者の要件として、会社の経営権(代表権)と所有権(議決権)の両方を握っている事が要求されます。
これはなぜかというと、単に所有権を持っているだけで経営に関与していないようなケースでは、中小企業の事業継続という事業承継税制の趣旨になじまないためです。
| 要件 | 贈与の場合 | 相続の場合 |
| 会社代表権 | 贈与前に会社代表権を持っており、 贈与時に会社代表権を持っていない事 |
相続前に会社代表権を持っていたこと |
| 議決権 | 贈与直前時点で、以下を両方充たす。 ・先代経営者本人と関係者合わせて議決権50%超 ・関係者の中で先代経営者が議決権を一番多く持っていたか、もしくは後継者に次いで多く持っていた事 |
相続直前時点で、以下を両方充たす。 ・先代経営者本人と関係者合わせて議決権50%超 ・関係者の中で先代経営者が議決権を一番多く持っていたか、もしくは後継者に次いで多く持っていた事 |
2.3 担保の提供の要件
事業承継税制を利用する場合には税額相当分の担保を税務署に提供する必要があります。
ただし、この制度の適用を受ける非上場株式そのものを担保にできるため、その他に担保を提供する必要はなく、実質的な負担は軽いと言えます。
2.4 会社の要件
一般的な中小企業であれば会社の要件を満たしており、事業承継税制の適用対象です。
適用除外される会社は主に下記の4種類あります。
・上場会社
・中小企業に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
※風俗営業会社とは、性風俗関連特殊営業事業を営む会社です。
このため、パチンコ業やゲームセンター等は含まれず事業承継税制を利用する事ができます。
※資産管理会社とは、事業運営目的というより、資産の管理・運用目的の会社です。
具体的には、総資産のうち70%以上が株式・不動産(自社利用分を除く)・現預金等で占められている、もしくは総収入額の75%以上が上記資産からの運用収入で占められている会社です。
3.事業承継税制を利用するための手続き
事業承継税制を利用するための手続きをご紹介します。
先代経営者が亡くなってからでも手続きは可能ですが、相続はただでさえスケジュールがタイトですので、事前に検討しておくことをお勧めします。
| タイミング | 必要手続き |
| 事前手続き | 特例承認計画を提出 |
| 贈与/相続 | 自社株式の贈与・相続を実行 |
| 事後手続き | ■最初の5年間 継続届出書・年次報告書を提出■6年目以降 継続届出書を3年に1回提出 |
4.事業承継税制を利用する場合の注意点
事業承継税制は中小企業の事業継続支援を趣旨としていることから、事業承継後も事業を継続していくことが求められます。
後継者が廃業した、事業を売却した、などの場合は課税の繰り延べが取り消されて税負担が発生し、場合によっては利子税が加算されるケースもあるため、注意が必要です。
ただし、1.2.1.でも触れました通り、経営悪化等が原因の場合は課税免除ないし減免の規定が設けられているため、過度に心配する必要はありません。
制度を悪用しての課税逃れを出来ないようにするという趣旨です。
課税繰延が取り消される具体的な要件、及び課税免除/減免のための要件は中小企業庁HPをご確認下さい。
まとめ
この記事では事業承継税制の特例措置の概要をご説明しました。
特例措置は従来の制度の問題点であった、将来的な課税リスクが大きく軽減され、事業承継時の税負担を事実上ゼロにすることができます。
特例措置は期限付きの措置ですので、将来的に事業承継をお考えの方はすぐに行動を起こすことをお勧めします。
関連記事
-

貸倒損失とは、売掛金が回収できなかった時に、費用として処理する方法です。 得意先から売掛金が入金されない事態となった時、まずは回収する努力が必要です。 それでもどうしても売掛金の回収ができない場合、売掛金の貸倒損失を損金算入できないかを検討しましょう。
-

経営者の皆さんは、節税商品として「オペレーティングリース」の紹介を受けたことはありますか。 オペレーティングリースのよくあるスキーム図では、登場人物が込み入っており、結局何をしているか、初見ではなかなか分からないと思います。 この記事では、オペレー
-

小規模企業共済は絶対入るべき!3つのメリットと知っておくべき注意点
小規模企業共済は、中小企業の役員や個人事業主の方で、所得税・住民税を節税したい、老後の資金の効率的な準備をしたい、と悩んでいる方におすすめしたい制度です。 手元に残るお金は、年収が800万円の場合、例えば毎月7万円の掛金を20年かけると、共済をやった
-

定番として取り上げられる節税策の中に、倒産防止共済が挙げられます。 (経営セーフティ共済とも呼ばれます) 倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産防止を趣旨とする共済ですが、実務においては節税策として使われることもよくあります。 しかし実は、倒産防止
-

会社から役員に対する報酬は、毎月の定額報酬ではなく役員賞与として受け取った方がお得という話を聞いたことは無いでしょうか。 この話は、場合によっては事実と言えます。 支給額の水準によっては、社会保険料が抑えられ、その分だけお得になるケースがあるからで
-

大きな利益が出ており、多額の法人税が発生する見込みの会社では、期末に駆け込みで経費を立てて、法人税額を減らそうとする事がよくあります。 典型的には、家賃等をまとめて前払いする(前払費用といいます)ケースです。 しかし、実際には、前払費用を支払ったタ
-

持ち家を買うと「住宅ローン控除」により所得税が下がるという事は皆さんもよくご存知と思います。 住宅ローン控除は、数ある所得税の控除制度の中でも節税効果の非常に大きな制度です。 しかし、住宅ローン控除の具体的な内容までは不動産会社等から説明されないこ
-

税金対策として、中古自動車を購入すると良い、という話を聞いたことがあると思います。 しかし、そのしくみを分かっていないと、税金対策したつもりが、まったく効果がないどころか、むしろ損をしてしまうリスクがあります。 そこで今回は、中古自動車を購入することが
-

貸倒引当金とは、売掛金の回収できない金額を事前に見込んでおいて、費用処理することです。 売掛金の回収が既にできなくなっている場合は貸倒損失を計上することにより、税金を減らすことができます(詳しくは「貸倒損失とは?回収できない債権を費用化できる条件」を
-

個人事業主の方は、原則として確定申告をする必要があります。 所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告の方が有利だということは、多くの方がご存知だと思います。 ただし、どのくらい青色申告の方がお得なのか、どういう方に青色申告が認められ