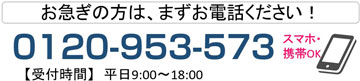自社事務所所有の方は固定資産税の減免制度を活用しましょう
- 2020年7月17日公開

コロナウイルスにより打撃を受けた事業者への支援策として、持続化給付金、雇用調整給付金に続き、家賃支援給付金の申請が始まろうとしています。(2020年7月以降)
ただし、この家賃支援給付金は家賃を支払っている事業者を対象としているため、事業者自身で事務所を所有している場合は対象となりません。
このような事業者のため、家賃支援給付金に代わる支援策として、2021年度分の固定資産税・都市計画税が徴収減免(軽減又は免除)される事となりました。
また、2020年度分については、固定資産税・都市計画税も含め、幅広い税目で1年間の徴収猶予が認められる事となりました。
この記事では、固定資産税・都市計画税の減免制度の概要、及び各税目の徴収猶予の概要をご説明します。
桐敷匠
最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)
- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日
- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日
- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日
目次
1. 固定資産税・都市計画税の減免制度とは
コロナの影響による固定資産税の減免制度について税理士が解説!
固定資産税・都市計画税の減免制度とは、事業者が一定の条項にある場合に固定資産税・都市計画税が減免される制度です。
減免が認められる状況は多岐に渡りますが、大きく分けて以下の2パターンあります。
(1)国の政策に沿ったなんらかの出費をした場合に特典として受けられるもの
(2)災害等を受けた場合に救済として特別に受けられるもの
今回のコロナウイルス対策は(2)のパターンに該当します。
条件を満たせば、2021年度の固定資産税・都市計画税が最大で100%免除されます。
※持続化給付金等と異なり、2020年度の減免ではない点にご注意下さい。
以下では、どのような事業者が減免を受けられるのか、いくら減免を受けられるのか、どんな手続きをすればよいかについて順にご説明します。
なお、コロナウイルスによる影響以外で、減免が受けられる状況については、各地方自治体に確認をお願いします。参考として、東京都の減免制度に関するwebサイトをご紹介します。
1.1. 固定資産税・都市計画税の減免要件
事業者がコロナウイルス対策で減免を受けるには、事業者要件と減収要件の2つの要件を満たす必要があります。
以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
1.1.1. 事業者要件
固定資産税・都市計画税を支払っている個人事業主、中小企業のほぼ全てが対象です。
ただし、対象業種に一部制限が掛かっており、性風俗関連特殊営業は除かれている点にご留意下さい。
また、持続化給付金では創業間もない事業者向けの救済措置が用意されましたが、本制度では今のところ同様の措置は用意されていません。今後、追加的な措置が取られる可能性がありますので、最近創業された方は中小企業庁等の関連サイトを定期的に確認する事をお勧めします。
| 事業者区分 | 法人 | 個人 |
| 事業者要件 | 資本金又は出資金1億円以下 資本金等の無い法人は従業員1,000人以下 ※大企業の子会社等は除外 ※性風俗関連業者は除外 |
従業員1,000人以下 ※性風俗関連業者は除外 |
1.1.2. 減収要件
今年2020年の2月~10月のうち、連続する3か月の売上が対前年同期比で30%以上下落している必要があります。
1.2. 固定資産税・都市計画税の減免額
減免額は売上減少の程度によって、全額免除と半額免除の2種類に分かれています。
| 売上減少率 | 免除額 |
| 今年の2月~10月のうち、連続する3か月の売上が対前年同期比で50%以上下落 | 全額免除 |
| 今年の2月~10月のうち、連続する3か月の売上が対前年同期比で30%以上下落 | 半額免除 |
1.3. 固定資産税・都市計画税の減免申請方法
減免を受けるためには、以下の2つの手続きが必要です。
・「認定経営革新等支援機関等」に申請要件を満たすか確認依頼をする
・市町村に軽減申告をする
それぞれ順番に説明します。
1.3.1. 「認定経営革新等支援機関等」に申請要件を満たすか確認依頼をする
事業者が減免要件を満たしているかどうか、あらかじめ認定経営革新等支援機関等に確認依頼をします。
税理士事務所によっては上記の支援機関として認定されている所もありますので、まずは顧問税理士に対して、認定を受けているかどうか確認をするとよいでしょう。
確認を依頼する際は登記簿謄本の写し、誓約書、売上減少が確認できる書類(試算表等)を提出する必要があります。
1.3.2. 市町村に軽減申告をする
認定経営革新等支援機関等に確認を受けると、確認書が発行されますので、上記書類一式と発行された確認書を合わせて、市町村に軽減申告を行います。
軽減申告ができる期間は2021年1月1日~31日までの一か月間と非常に短くなっていますので、今のうちから必要書類を揃えて、支援機関に相談しておくことをお勧めします。
2. 参考:徴収猶予も活用できる(国税・地方税一般)
徴収猶予とは、被災等、特定の事情がある事業者に対して、最大で1年間納税の猶予がされる制度です。
従来、徴収猶予を利用すると、延滞税が発生していましたが、新型コロナ税特法の成立・施行により、コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の場合は延滞税が免除されます。
対象となる税目は固定資産税・都市計画税に留まらず、国税・地方税のほとんど全てが対象です。
この制度はあくまでも猶予であって、免除ではない点にご留意下さい。
1年後には翌年分と合わせて2年分を払わなければなりません。
だとすると、本制度を利用するメリットは、
・一時的に資金繰りがラクになる
・延滞税が掛からない
ということになります。
以下では、どのような事業者が減免を受けられるのか、どんな手続きをすればよいかについて順にご説明します。
2.1. どのような事業者が徴収猶予を受けられるのか
2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、売上など、経常的な収入が前年同期比で概ね20%以上下落している場合に徴収猶予を受けることができます。
「経常的な」収入とある通り、持続化給付金などの臨時的な収入は計算から除外する事ができます。
本制度はあくまで徴収が猶予されるだけであるため、持続化給付金など他の支援策と比べると申請要件が緩くなっています。
2.2. どのような手続きをすればよいか
国税の場合は税務署に対して、地方税の場合は地方自治体に対して、それぞれ「納税の猶予申請書」「徴収猶予申請書」を提出することで猶予が認められます。
本来は納期限前の申請が必要ですが、納期限後であっても、やむをえない事情がある場合には認められる旨が記載されていますので、あきらめずに税務署や地方自治体に相談してみましょう。
まとめ
行政によるコロナウイルス対策として、持続化給付金、雇用調整助成金、家賃支援給付金等に加え、税金面でも事業者への支援策が出てきています。
税金面の支援策は持続化給付金等と比較すると申請の条件が緩くなっていますので、事業者の方はこれらも活用していきましょう。
関連記事
-

コロナウイルスの影響により打撃を受けた事業者に対して、行政がさまざまな支援策を打ち出しています。 持続化給付金、雇用調整給付金、感染拡大防止協力金、etc その施策の一つとして、今まさに、家賃を国が最大600万円負担する「家賃支援給付金」の申請が始
-

コロナウイルスにより打撃を受けた事業者への支援策として、持続化給付金、雇用調整給付金に続き、家賃支援給付金の申請が始まろうとしています。(2020年7月以降) ただし、この家賃支援給付金は家賃を支払っている事業者を対象としているため、事業者自身で事務