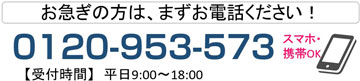増資とは?支配権に関する2つのリスクと対処法
- 2020年6月1日公開

事業拡大時の悩みの一つとして、資金調達が挙げられます。
資金調達の手段は大きく分けて、借入と増資の2種類があります。
このうち、増資とは、特に資金調達の場面においては新株を発行し、外部の投資家に引き受けてもらう事を意味します。
資金調達手段として見たとき、借入と比べると、増資は投資元本の返済義務や利払い義務を負わないなど、資金繰り上でメリットがあります。
一方、増資後は外部投資家が経営に参画する事になるため、会社の経営権が脅かされる等のリスクがあります。
よって経営者目線では、できる事なら借入の方が良いと言えます。
実際には、資金調達先の意向により、借入ではなく増資をするケースもあるでしょう。
しかし増資をする場合であっても、発行株式に特定の条件を設定する、すなわち種類株式を発行する事で上記リスクを軽減する事ができます。
この記事では、増資した場合の代表的なリスクと、リスクを軽減するために利用できる種類株式の制度をご紹介します。
桐敷匠
最新記事 by 桐敷匠 (全て見る)
- 住宅ローン控除の具体的な節税効果と適用条件 - 2021年5月5日
- オペレーティングリースとは?優秀な節税商品だがリスク有り - 2021年5月5日
- 事業再構築補助金とは?最大6000万円の支援を受けよう - 2021年2月16日
目次
はじめに|増資の2つのリスク
増資には以下の2つのリスクがあります。
1. 会社経営の自由が失われるリスク
2. 一旦増資を受けると資本関係を切るのが難しいというリスク
ただし、これらのリスクについては、対策もないわけではありません。
以下、それぞれについてお伝えします。
1.会社経営の自由が失われるリスクと対処法
1.1.増資により経営の主導権が損なわれるリスク
増資した場合、出資した側は会社の株主となり、経営に参画する権利が認められます。その結果、経営の自由が制約されるリスクがあります。
経営上の制約になりやすい主要な権利を以下に記載します。
| 株主の権利(株主権) | 要件(保有割合) | 経営上の制約 |
| 株主総会への出席権 | 1株以上 | 株主総会において、経営に関して株主から質問を受けた場合、説明する義務が生じます。 |
| 株主総会への議題提案権 | 3%又は300株以上 | 株主から株主総会の議題提案がなされた場合、議題を審議する義務が生じます。 |
| 特別決議に対する拒否権 | 1/3超 | 事業譲渡やM&A等の一定事項については、他の株主の同意なしに決議できなくなります。 |
| 会社支配権 | 1/2超 | 支配権を握った株主は会社の組織、運営、管理等に関する多くの事項について、経営者の同意なしに決議することが可能となります。
この結果、例えば投資家との関係が悪化した場合などで、投資家側の判断により経営者の座を追われる可能性もあります。 |
| 株主の権利(株主権) | 要件(保有割合) | 経営上の制約 |
| 株主総会への出席権 | 1株以上 | 株主総会において、経営に関して株主から質問を受けた場合、説明する義務が生じます。 |
| 株主総会への議題提案権 | 3%又は300株以上 | 株主から株主総会の議題提案がなされた場合、議題を審議する義務が生じます。 |
| 特別決議に対する拒否権 | 1/3超 | 事業譲渡やM&A等の一定事項については、他の株主の同意なしに決議できなくなります。 |
| 会社支配権 | 1/2超 | 支配権を握った株主は会社の組織、運営、管理等に関する多くの事項について、経営者の同意なしに決議することが可能となります。
この結果、例えば投資家との関係が悪化した場合などで、投資家側の判断により経営者の座を追われる可能性もあります。 |
1.2.対策|出資者のスタンスに応じて2通り
上記のリスクに対して取るべき対策は出資者のスタンスによっても変わってくるため、場合分けして記載します。
各対策はいずれも「種類株式の発行」によって行います。
種類株式とは、株式について特別な取り決めがなされた株式の総称です。
種類株式発行の手続は簡単
種類株式の発行には原則として株主総会特別決議が必要となりますが、実際にはオーナー企業であれば決議要件を満たすのは難しくなく、実務上の手続きについても、決議の省略規定等を活用できるため、そこまで難しいものではありません。
対策①|投資家側が経営への関与よりも経済的利益を重視している場合
会社法上、議決権のない株式、すなわち無議決権株式を発行することが認められています。(無議決権株式は種類株式の一種です。)
増資時の発行株式を無議決権株式としておけば、上記表にあるような株主権を制限することができます。
実務的には、無議決権株式とする代わりに優先配当を出す等、金銭面での見返りを付ける事が通常です。
(優先配当株式も種類株式の一種です。)
対策②|投資家側が経営への関与を望む場合
上記表にもある通り、投資家の持ち株比率が1/2超となった場合、投資家の一存で会社の経営方針を決議する事が可能となり、経営者側ではコントロールができなくなります。
このような場合の経営者側の最後の砦として、会社法では黄金株の設定が認められています。
黄金株も種類株式の一種であり、株式保有割合に関係なく、株主総会の決議事項を無効化する権利を持つ株式のことを言います。
あらかじめ経営者の持株を黄金株に設定しておけば、投資家側が株主総会で決議した事項に対して、経営者は拒否権を発動する事により無効化することが可能になります。
黄金株は何でも無効化できる訳ではなく、拒否権の対象となる事項を予め定めておく必要があります。
実務でよくある事例としては、経営者自身の選任・解任決議に拒否権を付けるケースです。
2.資本関係を切れないリスクと対処法
2.1.一旦出資を受けると資本関係を切るのが難しい
投資家が一度引き受けた株式は経営者側の意向で買戻す事ができず、原則として相手の同意が必要になります。
これが特に問題になるのは、経営方針等について後から仲違いした場合です。
経営者としては仲違いした株主を追い出したいのですが、相手が同意しない場合は買戻しができず、いつまでも相手方に株主としての権利が残ることとなります。
2.2.対策|増資時の発行株式に買戻し条件を付けておく
会社法上、一定の事由が生じた事を条件として、会社が相手方から株式を買戻す事が認められています。
買戻し条件を付与した株式の事を取得条項付株式と言い、これも種類株式の一種です。
「一定の事由」としてよくある例としては、「投資家側が出資契約違反をした」「特定の日付が到来した」「経営者が交代した」等様々です。
増資時の発行株式を取得条項付株式としておけば、後から株式の買戻しをすることが容易にとなります。
3.まとめ
増資時のリスクと、リスクを軽減するために活用できる種類株式をご紹介しました。
通常、増資時は資金の出し手側の方が強い立場にあります。しかし、増資にはリスクもありますので、経営者側としては新株の発行条件を丸飲みするのではなく、交渉の余地はないか検討する事をお勧めします。
また、そもそも経営者にとって著しく不利な増資であれば、増資を断る勇気を持つようにしましょう。
関連記事
-

コロナ禍にある中小企業等に向けて、「事業再構築補助金」の実施が決まりました。 家賃支援給付金等とは異なり、本制度は審査があるため、応募しても支援を受けられない可能性があります。 しかし、本制度の支援額はコロナ支援策の中でも飛び抜けて高額ですので、応
-

増資時に意識すべき税金と資本金の関係、及び増資時に取るべき対策
増資による資金調達をする際、調達額をいくらにすべきか悩むことは無いでしょうか。 調達額については前回記事でお伝えした通り、会社の支配権をどうするか、という資本政策的な観点での検討が必要です。 それに加えて、実は税負担の観点からも検討を加える必要があ
-

事業拡大時の悩みの一つとして、資金調達が挙げられます。 資金調達の手段は大きく分けて、借入と増資の2種類があります。 このうち、増資とは、特に資金調達の場面においては新株を発行し、外部の投資家に引き受けてもらう事を意味します。 資金調達手段と
-

経営者の皆さんは「経営革新計画」制度をご存知でしょうか。 中小企業が作成した経営革新計画を都道府県等の公的機関が一定の基準の下で審査し、承認する制度です。 承認が下りた企業は融資や税制、補助金申請などで様々な特典を受けることができます。 特に大き
-

中小企業や個人事業主にとって、設備投資の資金負担は非常に大きく、資金繰りに頭を悩ませる経営者の方も多くいらっしゃる事でしょう。 そんな時、真っ先に検討すべきはものづくり補助金です。「ものづくり」という名前ですが、製造業に限られません。サービスの提供や、業
-

貸借対照表と損益計算書は決算時に必ず作成する書類の一つです。 また、世間では、貸借対照表・損益計算書から算出した数値(財務指標)を経営に活用しようというような事がよく言われます。 しかし、経営者の中には、貸借対照表や損益計算書の読み方や財務指標の意